めざせ指人形マスター
キャラクターソフビ指人形をこよなく愛する一人の男が 「指人形マスター」と呼ばれることになる(といいな) までの顛末を記録した一代記である。
- 2025.07.12
[PR]
- 2007.02.05
アレックス・バーザ「ウソの歴史博物館」文春文庫
- 2007.01.30
京極夏彦著「百器徒然袋 雨、風」講談社ノベルス
- 2007.01.29
小学校アンサンブルコンテスト
- 2007.01.16
石田英一郎著「マヤ文明」中公新書
アレックス・バーザ「ウソの歴史博物館」文春文庫

訳者のあとがきによると、原題にあるHoaxというのは「嘘、ペテン、でっちあげ、ごまかし、まやかし、いたずら、インチキ、デマなど、とりどりの意味合いや色合いを持つカラフルな言葉」らしい。
この本には1700年代以前から現代まで世間に流布し、広く信じられたHoaxが図版とともに紹介されている。また紹介しきれない内容についてはホームページをみろ、とアドレスまで紹介されている。
勘違いしないでもらいたいのは「ああ、楽しくだまされた」という内容ばかりでは決してなく、詐欺まがい(完全に詐欺と呼べるものもある)だったり、デマに伴ってパニックが発生してしまったものも含まれている(面白かったのは、オーソンウェルズによる宇宙戦争のラジオドラマを大勢の人が信じてパニックになったという有名な話が、実はあまりパニックは発生しておらず、パニックが発生したということ自体がデマに近いものだったと考えられている、らしいということだった)。
年代が下るにつれてウソの内容も徐々に高度化?してくる。単なる風評が、新聞やラジオ、テレビ、インターネットというメディアによってさまざまに検証されるからである。
ただし、20世紀初めのころは反骨精神?あふれる記者たちが世の中への警鐘などともっともらしい理屈をつけて、ウソの記事を新聞にも掲載していたようだ。
いまではとても考えられない。
読み進むと気がつくのだが、ウソの表現方法は確かに高度化しているが、内容に大きな変化はないようだ。冷静に考えればありえないような話でも、テレビでとりあげられたり、だとか「権威ある人が話した」というだけであっさりと人は信じてしまうらしい。
信じないまでも「もしかしたらあるかもね」と思う人は多いだろう。むしろ現代のように「多様な価値観」を重視する風潮にあっては「絶対にありえない」などと主張する方が「あの人は意固地で頑固」などというきめ付けをされかねない。
この本は「ウソのアイデア」を楽しむ本ではない。ウソが人々の間で真実として浸透していく過程には何が起こっているのかを知るための本である。
特にテレビをみてすぐに納豆を買いに行ってしまったような人々には絶対に読んでもらいたいものだ。

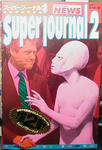
とは違い、「明らかな合成写真」のオンパレードだ。
この内容を信じる人がいたら、みんなで保護してあげないとあっとうまに全財産をむしりとられてしまうだろう。
もともとは「世界各地で発生している独占スクープとして他紙に先駆けて発表しているウィークリィ・ワールド・ニュース」のスクープ写真?を集めたものなのだが、なんというか、アイデア満載の写真に苦笑させられたり、感心させられたりする。(何冊発売されているのか知らない。発売当時に「VOWもびっくり」という言葉にひかれて、2冊目まで買ったが、そこでさすがに飽きてそれ以上探すのをやめてしまった。)
今ではこの手の合成写真はインターネット上にあふれている。各個人が気軽に情報発信できるようになったので、そんなウソ情報が世の中に氾濫しているのだ、とインターネットを悪者にする人も見かけるが、インターネットがあるからウソが生まれるのではなく、ウソがあるからインターネットにまで広まっていく、ということがこれらの本をみていると痛感するのである。
京極夏彦著「百器徒然袋 雨、風」講談社ノベルス
ひさしぶりに京極夏彦を読みました。「姑獲鳥の夏」からずっと読んでいたんですが、「塗仏の宴」で登場人物である『小説家 関口』の行動に嫌気が差ししばらく遠ざかっていました。
今回のこの本は定価がそれぞれ1000円以上もするところを2冊とも200円で売られていたので久しぶりに買ってみた、というわけです。
一冊に3つの中篇が入っていて2冊で合計6編を楽しむことができます。主人公(というか語り部)は「僕」こと「本島俊夫」。活躍する探偵は「榎木津礼二郎」。どの話も事件の規模としては比較的小さく、長編でとりあげられた事件の合間に発生した騒動、という位置づけになっています。
構成も凝っていて、一例をあげると
・6編につけられたサブタイトルは「薔薇十字探偵の●▲」で統一され、この「●▲」がお話の順番にしりとりになっている。
・それぞれの話はおおむね7章程度で構成されているが、各章の冒頭の言葉やシーンが統一されている。(同じ言葉が使われていたり、にかよった場面であったり・・)
・1冊目の最後のページで「僕」の苗字が「本島」であることが明かされ、2冊目の最後のページでフルネーム「本島俊夫」が初めて登場します。ストーリーにはまったく関係の無いことですが。
などがあげられます。
もともと京極夏彦の作品は推理小説の体裁をとりながらも「ストーリーでうならせる」というより、妖怪をはじめとするさまざまな小道具、薀蓄、キャラクターで読ませる「雰囲気重視」の作品が多いと思うのですが、この2冊は、その「キャラクター」を最大限に動かした結果うまれた、きわめて痛快な本であるといえます。
語り口も軽妙であるうえ、独特な癖のあるキャラクターたちを「僕」という極めて普通の人間の目を通して描いているために、数ページ読んではくすっ、また数ページ読んではプププ、と笑いがこみ上げてきます。
もちろん、他の長編を読んで各キャラクターの特質を理解しておかないと、この笑いを体験することはできませんが、根っからの京極ファンであれば十分に楽しむことができるでしょう。
しかし、榎木津というキャラクターに対してこのような破天荒な使い方があるとは思いもよりませんでした。彼には『他人の記憶を見ることができる』という体質?があるのですが、最初に「姑獲鳥の夏」で彼とであったときは『直接、犯罪やトリックに関係していない人が嘘や勘違いをしていないことを証明する』ためのキャラクターであり、この作者もうまく逃げているなぁ、としか思わなかったものです(詳しくは忘れましたが、推理小説につきもののジレンマだそうです。確かに証言すべてを疑っていては話が進みませんからねぇ)。
それが、この作品では傍若無人、快刀乱麻、完全粉砕と大活躍します。ただしこの便利すぎる体質のためか、それぞれのストーリー後半で事件収束のために突然現れる、といった使い方になっています。また、長編で探偵役をつとめた京極堂こと「中禅寺」も重要な役どころとして登場します。
事件のきっかけを作ったりいやおうなしに巻き込まれている、極めて普通人である「僕」、「僕」よりは変人であるがまだ理解可能な「榎木津の下僕(と呼ばれる探偵たち)」。彼らには理解不可能な事件のからくりを瞬時にして理解し彼らにわかりやすく伝える「中禅寺」、読者を含めてすべての登場人物(もちろん中禅寺を除いて)の意表をつく『力技』で事件を収束させる「榎木津」と人物配置も実に巧みです。
長編に登場する(私の大嫌いな)「関口」や、中禅寺の妹である「敦子」もところどころで顔を出してきます。未読の方はぜひ彼らの作り出す身近なように見えてとても不思議な世界を体験してみてください。
個人的な感想ですが、「榎木津」が「わははははは」と笑いながらやくざな人たちを叩きのめすシーンは「安永航一郎」画、がとても似合いそうです・・・・
小学校アンサンブルコンテスト
27日の土曜日に地元の文化会館で開催された「小学校アンサンブルコンテスト」のスタッフとして手伝いに出かけました。
いやあ、びっくりするぐらいに上手でした。コンテストは「リコーダー」と「管楽器」「打楽器」「管打楽器」に分かれていましたが、リコーダーアンサンブルはこういう機会でしか聞けないのでとても新鮮であり、その繊細な音色にはいつもうっとりさせられます。
管楽器や打楽器も驚くぐらい上手です。実行委員である知り合いの先生に
「いつの間にこんなにレベルが上がったの」
と聞くと
「数年前に音大生が各学校を回って指導したことがあって・・・」
とのこと。確かに音楽というのは良いものを聞けば聞くほど上達するものですが、それにしてもうまかったです。
「小学校でこれだけレベルが高いのに、中学になると少しレベルが下がるのはなぜ?」
中学校の部活指導の手伝いをしていることから、コンクールを聞く機会も多いので、その経験からたずねてみました。
「中学で吹奏楽部に入るとは限らないから・・・」
どうも、小学校のクラブで燃え尽きてしまうようです。
指導の先生が熱心でうまくなればなるほど(音楽というものに上手の限界はありませんが)、「もういいや」と思ってしまうそうです。
「もったいないなぁ」
と正直な感想を述べたらその先生は苦笑いしていました。
たしかにコンクールに出場するような学校では『コンクールで賞をとる』というのはとても大切なことだと思いますし、出場する子供たちもそれがひとつの目標だとは思います。
でも、それ以上に『音楽は楽しいものだ』ということを教えてあげることが大切だとも思うのです。
楽しいからこそつらい練習も耐えられるし、さらに上手になろうとがんばれるし、僕のように40過ぎても音楽を趣味として生きていけるようになると思うのですが・・・・・
石田英一郎著「マヤ文明」中公新書

この本は秋にわが町で開催されるブックリサイクル (無料配布)で手に入れたのですが、奥付をみてびっくり!「昭和42年3月25日」の版でした。
古いなぁと思いつつ、興味がわいたら最新の情報を改めて調べればいいや、と読み始めましたんですが、正直言って参りました。
マヤ文明はもともと中央アメリカ(アメリカ大陸と南米大陸をつなぐ橋みたいなところね)に会ったらしいのですが、このあたりはコーヒーの産地である「グァテマラ」という地名を知っているぐらいでほとんど馴染みがありません。(だから興味を持ったのですが)
だから本文中にでてくる固有名詞が地名なのか人名なのか、位を示しているのか単位を示しているのか、読んでいるうちに覚え切れなくて混乱してくるんですね。
それでもせっかくだから、と読み進んだ結果、マヤ文明は他の文明(我々の世代でいうところの四大文明)に比べて道具類(金属器や車輪など)が未発達なのに比べて、天文暦・ゼロを含む単純化された数字、複雑な神聖文字、優雅で格調の高い美術工芸は四大文明以上である、ということがわかりました。
・・・・ってこの程度ならばマヤ文明を解説・紹介しているホームページ(例えばここ)を見れば手に入る情報だったりしますが、読み慣れないカタカナが続く文章に苦労したあとなので、なんかすごく納得した、というか理解したような気になりました。
もう一度読み返すと、もう少し理解できるかもしれませんね。
こんな調子なので、本はたくさん読みますが、海外文学はとても苦手です。特に中国文学は苦手。
カタカナなら「覚えきれんなぁ」ですむんですが、中国文学だと「覚えきれんなぁ+なんて読むんだぁ」となってストレスがたまります。
日本のものでも平安時代より前を舞台にした物語も同じように苦手ですねぇ
「嵯峨治世初期は、太政官筆頭だった藤原園人の主導のもと、百姓撫民(貧民救済)そして権門(有力貴族・寺社)抑制の政策がとられた。これは、律令の背景思想だった儒教に基づく政策であったが・・・(Wikipedia 平安時代の項より)」
という文章が続くとちょっと疲れます・・・
話がそれましたが、この「マヤ文明 世界史に残る謎」を読んだことで
「この間マヤ文明の本を読んだんだけどさぁ」
と言えますね。

